相続のことなら『東京相続なんでも相談ルーム』へご相談下さい。
休日:土曜・日曜・祭日
相続税が課税される財産〜みなし相続財産〜
2025.4.6更新
相続税が課税される財産として、相続税法には「みなし相続財産」の規定があります。「みなし相続財産」は「本来の相続財産」とは異なり、被相続人が所有していた財産で相続人等に承継された財産ではないのですが、被相続人の死亡に伴い相続人等が経済的利益を得ることとなる実態が、相続又は遺贈による財産承継と同様であることから、相続税法上、相続税が課税される財産として取り扱われます。
相続税法に規定されている『みなし相続財産』
相続税法に規定されている「みなし相続財産」は次のとおりです。
【相続又は遺贈により取得したものとみなす財産】
| 生命保険金または損害保険金 | 相続税法第3条①一 |
| 退職手当金、功労金など | 相続税法第3条①二 |
| 生命保険契約に関する権利 | 相続税法第3条①三 |
| 定期金に関する権利 | 相続税法第3条①四 |
| 保証期間付定期金に関する権利 | 相続税法第3条①五 |
| 契約に基づかない定期金に関する権利 | 相続税法第3条①六 |
| その他の利益の享受 | 相続税法第4、7、8、9条 |
| 信託に関する権利 | 相続税法第9条の2~9条の6 |
生命保険金等(相法3①一)
被相続人の死亡により、相続人その他の者が取得した、生命保険金や損害保険金で、被相続人が負担した保険料に対応する部分の保険金が、相続財産とみなされます。
保険金受取人は、保険契約に基づいて、保険会社から保険金を受け取る権利を持っており、取得した保険金は、被相続人から承継した財産ではありません。しかし、相続税法では、被相続人が保険料を負担しているという事実に着目し、被相続人の財産が保険契約を通じて、保険金受取人に承継されたと考えるのです。
被相続人の死亡を保険事故として保険金が支払われる生命保険契約等で、保険料を実質的に被相続人が負担しているものについては、みなし相続財産として取り扱われますので、相続税の申告に際しては、相続財産に含めなければなりません。
相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には、保険金受取人が保険金とともに取得する以下の金銭を含むことにもご留意下さい(相基通3-8)。
- 保険契約に基づき分配を受ける剰余金
- 割戻しを受ける剰余金
- 払戻しを受ける前納保険料
退職手当金、功労金等(相法3①二)
被相続人の死亡により、相続人その他の者が取得した、本来ならば被相続人に支給されるべきであった退職手当金・功労金等は、相続財産とみなされます。但し、退職手当金・功労金等のうち「みなし相続財産」として取扱われるのは、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。実際に支給される時期が被相続人の死亡後3年経過後でも、死亡後3年以内に支給額が確定していれば相続財産に含めなければなりません(相基通3-30)。
「みなし相続財産」とされる退職手当金・功労金等は、その名義のいかんにかかわらず、実質上被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます(相基通3-18)。
留意する点は「弔慰金等」の取扱いです。被相続人の死亡により受け取る弔慰金、花輪代、葬祭料等は、遺族に対する弔意を表すものですから、社会通念上一般的な範囲のものは、課税されません。しかし、名目上、弔慰金や花輪代として支給され、実質は退職手当金・功労金等と変わらないというケースも想定されます。したがって、弔慰金等として支給された金品であっても、退職手当金・功労金等として課税対象である相続財産に含める基準が、以下のとおり設けられていますのでご留意下さい(相基通3-20)。
- 被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、雇用主等から受ける弔慰金等のうち、被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分を超える部分の金額は退職手当金・功労金等として相続財産に含まれます。⇒課税されない弔慰金等は普通給与の3年分
- 被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合、雇用主等から受ける弔慰金等のうち、被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分を超える部分の金額は退職手当金・功労金等として相続財産に含まれます。⇒課税されない弔慰金等は普通給与の6ヵ月分
生命保険契約に関する権利(相法3①三)
相続開始時には保険事故が発生しておらず、保険金の支払いがない場合でも、「生命保険契約に関する権利」として相続税が課税される場合があります。
みなし相続財産とされる「生命保険契約に関する権利」は、次の要件を満たす場合、生命保険契約の契約者の相続財産とみなされます。
- 相続開始時点で、保険事故が発生していない生命保険契約であること。これは、被相続人が被保険者ではない生命保険契約であることを意味します。
- 被相続人以外の人が、生命保険契約の契約者であること。これは、被相続人が、生命保険契約の契約者ではないことを意味します。
- 被相続人が保険料を負担していること。
「生命保険契約に関する権利」についても、被相続人が保険料を負担していることに着目し、生命保険契約の契約者が、被相続人が負担した保険料に対応する部分の利益を享受するものと考えます。
「生命保険契約に関する権利」の価額は、相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価されます(評基通214)。解約返戻金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分の金額が、みなし相続財産として相続財産に加算されます。
「生命保険契約に関する権利」は、被相続人の死亡による保険金の支払いがないので、申告漏れになり易い相続財産ですので、ご留意下さい。
また、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約の契約者が被相続人であり、被相続人自身が保険料を負担している場合には、その保険契約は「本来の相続財産」となり、相続人その他の者が、相続又は遺贈により取得することとなります(相基通3-36(1))。
定期金に関する権利(相法3①四)
相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で、被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の人が、その定期金給付契約の契約者である場合、被相続人が負担した掛金又は保険料に対応する価額は、契約者のみなし相続財産となります。
保障期間付定期金に関する権利(相法3①五)
保証期間付定期金とは、定期金受取人に対して生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、その定期金受取人が死亡したときには、定期金受取人の遺族その他の者に対して、定期金又は一時金を給付するものとする定期金給付契約のことです。
この定期金給付契約に基づいて、被相続人である定期金受取人に引き続き、相続人その他の人が、定期金受取人又は一時金受取人となった場合、被相続人が負担した定期金給付契約の掛金又は保険料に対応する金額は、定期金受取人又は一時金受取人のみなし相続財産となります。
契約に基づかない定期金に関する権利(相法3①六)
契約に基づかない定期金として、次のものが挙げられます。
- 退職年金の継続受取人が取得する受給権
- 国家公務員共済組合法の規定による遺族年金
- 地方公務員等共済組合法の規定による遺族年金
- 船員保険法の規定による遺族年金
- 厚生年金保険法による遺族年金
2~5の遺族年金については、それぞれの法律に非課税規定が設けられていますので、相続税は課税されません(相基通3-46)。したがいまして、1の退職年金の受給権がみなし相続財産となります。なお、退職手当金等が定期金として支給される場合は、契約に基づかない定期金に関する権利(相3①六)としてではなく、退職手当金等(相3①二)として取扱います(相基通3-47)。
その他の利益の享受(相法4、7、8、9)
その他の利益の享受としてまとめられるものは、次のとおりです。
| 相続財産法人から分与を受けた財産 | 相続税法第4条 |
| 低額譲受 | 相続税法第7条 |
| 債務免除、債務引受・弁済により得た利益 | 相続税法第8条 |
| その他の利益の享受 | 相続税法第9条 |
信託に関する権利(相法9の2〜9の6)
委託者または受益者等の死亡を起因として、適正な対価を負担せずに、新たに信託の受益者等になった場合や、信託に関する利益を受けた場合、その利益を受けた人が、信託財産等を遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。
相続放棄をしても課税されます
みなし相続財産の規定は、契約等に基づく固有の権利を持つ人が、被相続人の死亡をきっかけに享受した経済上の利益を相続財産とみなしています。
例えば、相続人ではない人が、保険契約上の権利に基づき、被相続人の死亡を保険事故として支払われる死亡保険金を取得したという場合、遺贈により財産(保険金)を取得したものとみなされ、相続税が課税されるのです。
したがって、相続を放棄して、本来の相続財産は取得していなくても、被相続人の死亡に起因する保険金等を受け取っている場合は、その保険金等のみなし相続財産を、遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されることとなります。
遺産分割の対象にはなりません
みなし相続財産は、相続税法上、相続財産として課税されるものであって、民法上の相続財産(=本来の相続財産)ではありません。
また、みなし相続財産は契約等に基づく固有の権利であり、契約者等が有する固有の財産でありますので、遺産分割の対象とされる共同相続人の共有財産を構成するものではありません。
したがいまして、みなし相続財産は、遺産分割の対象にはなりません。
みなし相続財産を遺産分割の対象財産に含めて遺産分割を行ってしまいますと、みなし相続財産を取得した相続人等に相続税が課税され、そのみなし相続財産を分割により取得した他の相続人には、贈与税が課税されてしまうということが生じます。みなし相続財産を遺産分割の対象財産に含めないようにご注意下さい。
『みなし相続財産』と非課税財産について
みなし相続財産のうち『生命保険金等(相法3①一)』と『退職手当金等(相法3①二)』については、非課税限度額が設けられています。
いずれも次の算式により、非課税限度額が計算されます。
500万円×法定相続人の数
上記の算式により計算された限度額までは、相続税が課税されませんので、節税対策の第一歩として生命保険契約が利用されます。
- 相続不動産の税金
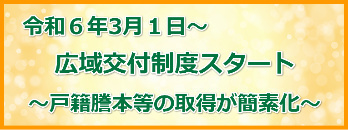
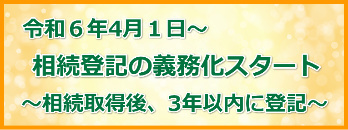
ご連絡先&アクセス
地図
小林佳与公認会計士・税理士事務所
住所
〒143-0023
東京都大田区山王2-1-8
山王アーバンライフ310
JR京浜東北線根岸線・大森駅
北口より徒歩1分
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。

