相続のことなら『東京相続なんでも相談ルーム』へご相談下さい。
休日:土曜・日曜・祭日
相続税の計算方法
2025.3.29更新
相続税額の計算方法は、次のとおりです。計算手順を10のステップに分けて記しています。各ステップごとに、相続税法等に細かな規定があり、相続税法特有の考え方が反映されています。各ステップについての解説は別ページにまとめてありますが、計算の流れを知ると、相続税額を計算するに際して重要となるポイントが理解し易くなります。
まずは、相続税計算の大局をお確かめください。
相続税が課税される財産の把握
相続税が課税される財産は、本来の相続財産とみなし相続財産に分けて把握します。
本来の相続財産は、一般的に「金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの」と説明されます。相続税の計算に際しては、本来の相続財産の「金銭に見積もる」すなわち「評価」が重要ポイントとなります。「評価」について、相続税計算に特有の財産の評価方法がありますので、基本的には、その財産評価法に則って評価することとなります。
みなし相続財産は、相続税法が特別に定める相続財産です。被相続人から、直接、相続または遺贈により承継した財産ではないけれども、相続財産とみなして相続税が課税される財産です。代表的なみなし相続財産は、『死亡保険金』や『退職手当金』です。
非課税財産の把握
相続税法等において、7種類の財産が非課税財産として定められています。国民感情への配慮、公益性、社会政策的な見地から、非課税財産が定められています。
債務控除のための債務等の把握
相続税は、プラスの財産(=課税財産)からマイナスの財産を差し引いた純財産に課税されます。マイナスの財産である債務と葬式費用を課税財産から控除することを、債務控除といいます。葬式費用は被相続人が残したマイナス財産ではありませんが、相続税法上、控除が認められています。債務控除額を計算するために、債務と葬式費用を把握します。
相続時精算課税に係る贈与財産の把握
相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産がある場合、その贈与財産の価額は、相続税の課税価格に含まれます。相続税の課税価格に加算される相続時精算課税適用財産の価額は、贈与時の価額であることに要注意です。
暦年課税分の贈与財産の把握
相続人または受遺者が、相続開始前7年以内に、被相続人から暦年課税の贈与により取得した財産がある場合、その贈与財産の価額は、相続税の課税価格に加算されます(生前贈与加算)。相続税の課税価格に加算される贈与財産の価額は贈与時の価額です。但し、相続開始前4年から7年の贈与財産総額から100万円を差引くことができます。
課税価格の計算
課税価格は、相続税の課税対象となる金額です。課税価格は財産を取得した各人毎に計算します。次に、各人毎に計算した課税価格を合計します。
課税価格=(相続税が課税される財産-非課税財産)-債務控除+相続時精算課税適用財産の価額+暦年贈与財産の価額
(注1)相続税が課税される財産-非課税財産=取得財産の価額
(注2)相続税申告書(第1表)上の計算順序とは異なります。
課税遺産総額の計算
課税価格の合計額から、遺産に係る基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
課税遺産総額=課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額
相続税の総額の計算
- 法定相続人・代襲相続人が、法定相続分・代襲相続分を相続したものと仮定して、各法定相続人・代襲相続人の取得財産額を計算します。(指定相続分は使いません。)
- 各法定相続人・代襲相続人の取得財産額に、それぞれに適用される税率を乗じて、各法定相続人・代襲相続人ごとの相続税額を算出します。
- 各法定相続人・代襲相続人ごとに計算された相続税額を合計して、相続税の総額を計算します。
各人の算出税額の計算
実際に財産を取得した人の相続税額は、相続税の総額を按分して計算します。
按分割合は「各人の課税価格」を「課税価格の合計額」で除して算出します。
按分割合=各人の課税価格÷課税価格の合計額
相続税の総額に按分割合を乗じて、各人の算出税額を求めます。
各人の算出税額=相続税の総額×按分割合
さらに「相続税額の2割加算制度」の対象者には、各人の算出税額に、2割相当の税額が加算されます。
各人の納付・還付税額の計算
財産を取得した人ごとの納付税額または還付税額を計算する際には、財産取得者各々に適用される税額控除等を加味します。具体的には、以下の控除項目等があります。
- 相続不動産の税金
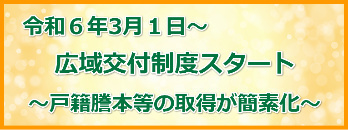
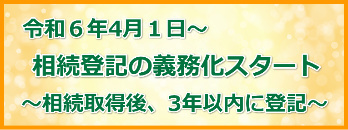
ご連絡先&アクセス
地図
小林佳与公認会計士・税理士事務所
住所
〒143-0023
東京都大田区山王2-1-8
山王アーバンライフ310
JR京浜東北線根岸線・大森駅
北口より徒歩1分
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。

