相続のことなら『東京相続なんでも相談ルーム』へご相談下さい。
休日:土曜・日曜・祭日
相続税が課税される財産〜本来の相続財産〜
2025.4.6更新
相続税が課税される「本来の相続財産」とは、「被相続人が生前に所有していた財産で、金銭に見積もることができる経済的価値のあるもののすべて」と説明されます。
「本来の相続財産」とは具体的にどのようなものなのかを例示し、また、「本来の相続財産」を把握して相続税額を計算する際の留意点を、以下に解説致します。
本来の相続財産の種類・細目
「本来の相続財産」の具体的な種類とその細目を以下に例示します。
権利や無形資産については、イメージしにくいものもありますが、大部分が「財産価値のあるもの」、言い換えますと「金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの」として、容易にイメージできるのではないでしょうか。皆様の日常生活のなかで、通常、財産価値があると考えられるものが「本来の相続財産」であると言えるでしょう。
| 種類 | 細目 |
| 土地 (土地の上に存する権利を含む。) | 宅地 |
| 田 | |
| 畑 | |
| 山林 | |
| その他の土地(牧場、原野、池沼など) | |
| 家屋 | 家屋・構築物 |
| 事業(農業)用財産 | 機械、器具、農機具、その他の減価償却資産 (無形資産も含む。) |
| 商品、製品、半製品、原材料、農産物等 | |
| 売掛金 | |
| その他の財産 | |
| 有価証券 | 株式、出資 |
| 公債、社債 | |
| 証券投資信託、貸付信託の受益証券 | |
| 現金・預貯金 | 現金、普通預金、当座預金、定期預金、金銭信託など |
| 家庭用財産 | 家具、備品、書画、骨董品、宝石など |
| その他の財産 | 立木 |
国税庁公表「相続税の申告のしかた」より
名義財産について
名義財産は、「実質的な所有者とは異なる名前が付されている財産」です。代表的なものとして、名義預金・名義株が挙げられます。この名義財産が、「本来の相続財産」に含まれるか否かという点で、見解が分かれることがあります。
具体例として、被相続人である父親が、息子のために、息子名義の預金をしていた場合、この息子名義の預金が、相続財産に含まれるのかどうかを考えてみましょう。息子名義の預金について、亡き父親が資金を拠出し、通帳、印鑑等の管理も父親が行っており、さらに、息子自身はこの預金の存在を、相続開始まで知らなかったという場合は、たとえ名義が息子の名前になっていても、父親の所有財産として、「本来の相続財産」に含まれます。
「本来の相続財産」は「被相続人が生前に所有していたもの」です。この「所有していた」ということを実質的に解する点に注意が必要です。税務調査では、所有権が移転していないこと、すなわち、贈与は成立していないことが争点となります。上記の具体例は、非常に分かり易い例ですが、実質的な所有者は誰なのかを容易に判断できない場合もあります。
後日、税務当局と見解が分かれることのないように、名義財産を漏れなく把握し、その実質的な所有者を慎重に判断する必要があります。
本来の相続財産の評価について
本来の相続財産」は「金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの」です。
それでは、上記「本来の相続財産の種類・細目」にあるような種々の相続財産を、どのように「金銭に見積もる」のでしょうか。
相続財産を金銭に見積もることを、「財産を評価する」と言います。
この財産評価について、相続税法第22条に評価の原則として次のような記述があります。
「相続税法第22条【評価の原則】この章(相続税法第三章)で特別の定めのあるものを除くのほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。」
相続税法第三章は財産の評価について規定されていますが、一部の財産についてのみ具体的評価方法が記述されているにとどまります。したがって、大部分の財産については、相続税法上、時価で評価するとしか規定されていません。ここで、「時価とは、どのような価額か?」という点が検討課題となります。
この点、国税庁は「財産評価基本通達」を定め、財産評価方法の統一を図っています。したがって、「本来の相続財産」は、基本的に「財産評価基本通達」に則って評価することとなります。
「財産評価基本通達」は法律ではありませんので、納税者が従わなければならない義務はありませんが、実務上、税務当局が「財産評価基本通達」に則って、納税者による財産評価の是非を検討していることから、納税者が財産評価をする際にも、「財産評価基本通達」を参照することとなったという経緯があります。
- 相続不動産の税金
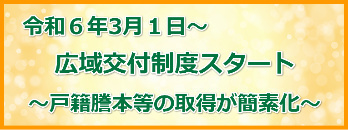
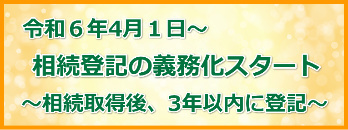
ご連絡先&アクセス
地図
小林佳与公認会計士・税理士事務所
住所
〒143-0023
東京都大田区山王2-1-8
山王アーバンライフ310
JR京浜東北線根岸線・大森駅
北口より徒歩1分
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。

