相続のことなら『東京相続なんでも相談ルーム』へご相談下さい。
休日:土曜・日曜・祭日
法定相続人について
2025.4.2更新
相続税の計算に際して、「法定相続人」を確定することは非常に重要な作業であり、間違いは許されません。
「法定相続人」とは何を意味するのか?また、なぜ重要なのかについて、皆様のご理解が深まれば幸いです。是非、ご覧下さい。
相続人と法定相続人について
相続税法においては、「相続人」と「法定相続人」を区別して、各種規定が定められています。
相続人は、民法に定められている相続人から、相続を放棄した人と相続権を失った人を除きます(相続税法第3条第1項本文)。つまり、相続人は、民法に定める相続権があり、相続を承認し、実際に財産を相続した人となります。
一方、法定相続人は、民法に定められている相続人のことであり、相続を放棄した人がいる場合でも、相続放棄がなかったものとして取扱います(相続税法第15条第2項)。
民法第5編第2章に定められている相続人は、次のとおりです。
| 配偶者相続人 | |
| 配偶者 | |
| 血族相続人 | |
| 第1順位 | 子及びその代襲相続人(孫・ひ孫等) |
| 第2順位 | 直系尊属 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹及びその代襲相続人 |
- 配偶者は常に相続人になります。配偶者は法律上の婚姻関係にある者に限定されます。
- 第1順位の相続人がいる場合、第2順位の父母や、第3順位の兄弟姉妹は相続人になることは出来ません。
- 第2順位の直系尊属が複数人いる場合は、親等の近い者から相続人となります。
- 第1順位の相続人には再代襲(2回目の代襲)が認められていますが、第3順位の兄弟姉妹には代襲相続は1回しか認められません。
法定相続人の数について
前述のとおり、法定相続人は、民法第5編第2章に定められている相続人のことであり、相続放棄者がいる場合には、相続放棄がなかったものとして取扱います。相続税法上、このような法定相続人の規定が設けられているのは、特に「法定相続人の数」を用いて控除額を計算する規定があるからです。
例えば、遺産に係る基礎控除額は下記の算式で求められます。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
この算式の「法定相続人の数」を「相続人の数」に置き換えて考えてみましょう。「相続人の数」と規定されていれば、意図的に相続人の数を増やして、控除額を大きくすることが可能となります。被相続人の配偶者と一人っ子が相続放棄をすることにより、被相続人の5人の兄弟姉妹が相続人となり、相続人の数が増えるケース等が考えられます(第2順位の相続人はいないものと想定)。
意図的に、相続を放棄して相続人の数を増やし、控除額を大きくするというような潜脱行為を防ぐために、相続の放棄があったとしても、人数の変動しない法定相続人を規定しているのです。
『法定相続人の数』を適用する規定
「法定相続人の数」を使って計算する規定は、次のとおりです。
- 遺産に係る基礎控除額の計算
- 生命保険金等の非課税額の計算
- 退職手当金等の非課税額の計算
- 相続税の総額の計算
いずれも相続税の計算上、非常に重要な規定です。
養子についての規定
「法定相続人の数」を意図的に増やす余地をなくすために、さらに、相続税法には「養子の数」についての規定があります。
民法上は、養子が何人いても、法定血族(法律上の手続きを経て血のつながりが認められている者)であれば、相続人となります。この考え方を相続税法にそのまま適用しますと、やはり潜脱行為の機会を与えてしまいます。意図的に「養子の数」を増やして、「法定相続人の数」を増やすことが出来るからです。
そこで、相続税法は、このような操作が出来ないように、「法定相続人の数」に含めることが出来る「養子の数」を制限しています。
- 被相続人に実子がある場合、または、被相続人に実子がなく、養子の数が1人の場合、法定相続人の数に含める養子の数は1人。
- 被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上の場合、法定相続人の数に含める養子の数は2人。(相続税法第15条第2項各号)
養子縁組により、2人以上の養子がいても、法定相続人の数にカウントされるのは、最大でも2人だけとなります。
上記の「養子の数の制限規定」は、相続税の計算上の取扱であり、「法定相続人の数」にカウントされなくても、法定血族である養子には、民法上の相続権が認められますので、相続人として財産を取得することはできます。もちろん、財産を相続すれば納税義務も生じます。この点にご注意ください。
法定相続人の確定方法
相続税の計算では、「法定相続人」を正しく確定しなければ、控除額等が正しく計算されず、その結果、相続税額が過大になってしまうことも考えられます。
「法定相続人」を正しく確定するために、次の手続きを行います。
被相続人の戸籍の入手
被相続人の出生から死亡までの戸籍を入手します。本籍地に変更があり、複数の市区町村から戸籍を入手する場合は、戸籍が連続していることを、必ず確かめなければなりません。
戸籍は本籍地の市区町村のみでしか取得できませんでしたが、令和6年3月1日から『広域交付制度』がスタートしましたので、最寄りの市区町村の窓口から他府県の市区町村にある戸籍謄本等を取得できるようになりました。
相続人が被相続人の出生から死亡までの戸籍を入手する場合、相続人の最寄りの市区町村窓口で一括して取得申請をすることができます。
相続人の戸籍の入手
(1)相続人が第1順位(=子等)の場合
相続人の生存を確認するために、現在の戸籍を入手します。
(2)相続人が第2順位(=直系尊属)の場合
- 第1順位の相続人(=子等)の戸籍を入手します。被相続人の戸籍から、子等がいないことが判明する場合は、第1順位の相続人の戸籍の入手は不要です。被相続人の戸籍から子等がいることが判明した場合は、その子等の死亡の記載のある戸籍を入手します。
- 第2順位の相続人の生存を確認するために、第2順位の相続人の現在の戸籍を入手します。
(3)相続人が第3順位(=兄弟姉妹)の場合
- 第1順位の相続人(=子等)の戸籍を入手します。(2)と同様。
- 第2順位の相続人(=直系尊属)の出生から死亡までの連続した戸籍を入手します。この場合、兄弟姉妹の存在を確認するために、被相続人の父と母の双方の出生から死亡までの戸籍を入手します。(半血の兄弟姉妹も相続人になるため。)
- 第3順位の相続人の生存を確認するために、第3順位の相続人の現在の戸籍を入手します。
- 相続不動産の税金
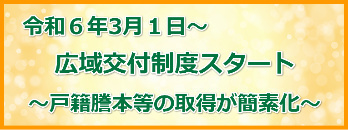
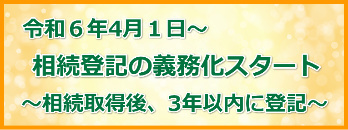
ご連絡先&アクセス
地図
小林佳与公認会計士・税理士事務所
住所
〒143-0023
東京都大田区山王2-1-8
山王アーバンライフ310
JR京浜東北線根岸線・大森駅
北口より徒歩1分
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。

