相続のことなら『東京相続なんでも相談ルーム』へご相談下さい。
休日:土曜・日曜・祭日
小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4)
~居住用宅地等への特例適用を解説~
2025年10月9日更新
租税特別措置法第69条の4『小規模宅地等の特例』を適用しますと、次のとおり宅地等の相続税評価額を減額することができます。
- 居住用宅地等・・・80%減額(330㎡まで)
- 事業用宅地等・・・80%減額(400㎡まで)
- 貸付事業用宅地等・・・50%減額(200㎡まで)
宅地等の相続税評価額を減額できるということは、相続財産の総額を小さくできますので、相続税を節税することができるということです。
相続財産に宅地等を含む場合には、相続税の節税対策として、先ずはこの特例を適用できるかどうかを検討しましょう。
相続税評価額を大きく減額する特例ですので、要件は詳細に定められています。下記の要件についての解説を御確認ください。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(概要)
租税特別措置法第69条の4には『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』が規定されています。一般に『小規模宅地等の特例』と言われています。
生活や事業の基盤となっている土地等に対する課税を緩和する規定ですので、居住用の宅地や事業に利用している土地などが相続財産に含まれているケースでは、この特例を適用することで、宅地等の相続税評価額を大幅に減額できます。
生前対策の一環として、特例の内容と適用要件を知って頂き、可能な限りご活用頂きたい特例です。
特例を適用することができる『小規模宅地等』は、次のとおり区分されています。
- 居住用宅地等
- 事業用宅地等
- 同族会社事業用宅地等
- 貸付事業用宅地等
上記1から4の区分の最後に『等』と付いているのは、それぞれ土地だけではなく、『土地の上に存する権利』、例えば『借地権』なども含むことから『等』と付いています。
『被相続人等の居住用宅地等』の意味
被相続人が老人ホーム等の施設に入居していた場合の取扱い
特例の適用対象となる『居住用宅地等』は、『被相続人が相続開始直前まで住んでいた』という要件が必要とされています。
しかしながら、昨今の相続では、被相続人が相続開始直前には老人ホームなどの施設に入居しているケースが多く見受けられます。このようなケースに対応すべく、老人ホームなどの施設に入居する直前まで被相続人が居住していた家屋の敷地等も、『居住用宅地等』に含まれることになっています。
相続開始の直前に、被相続人が施設に居住していた場合でも、小規模宅地等の特例の適用が認められるためには、下記の要件を満たさなければなりません。
【被相続人の状況】
- 相続開始直前に、要介護認定を受けていること。(介護保険法第19条第1項)
- 相続開始直前に、要支援認定をうけていること。(介護保険法第19条第2項)
- 相続開始直前に、厚生労働大臣が定める基準に該当する介護保険第一号被保険者であること。(租税特別措置法施行規則第23条の2第2項)
- 被相続人が、障がい支援区分の認定を受けていること。
※上記の『被相続人の状況1~3』については、老人ホーム等に入居する時点において要介護認定等を受けていない場合であっても、被相続人が相続開始の直前において要介護認定等を受けていればよいとされています。
【入所・入居していた施設等】
被相続人の状況が上記の1~3に該当する場合
- 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居(老人福祉法第5条の2第6項)
- 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
- 特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5)
- 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)
- 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
- 介護老人保健施設(介護保険法第8条第28項)
- 介護医療院(介護保険法第8条第29項)
- サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項)
被相続人の状況が上記の4に該当する場合
- 障がい者支援施設(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項)
- 共同生活援助を行う住居(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項)
【居住用宅地等の状態】
- 事業の用に供していないこと。
- 被相続人と被相続人と生計を一にしている親族以外の者が、居住の用に供していないこと。
《参考》国税庁質疑応答事例
老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合
【質疑】
老人ホームに入所していた被相続人が、要介護認定の申請中に亡くなり、相続開始の時に要介護認定を受けていませんでした。この場合において、相続開始後に要介護認定があったときには、相続開始の直前に要介護認定を受けていた被相続人に該当するものと考えられるでしょうか?
【回答】
被相続人は、相続開始の直前に要介護認定を受けていた者と認められます。
【解説(抜粋)】
老人ホームに入所していた被相続人が、要介護認定等の申請中に相続が開始した場合で、その被相続人の相続開始の日以後に要介護認定等があったときには、要介護認定等はその申請のあった日にさかのぼって、その効力が生ずることとなります。要介護認定等が行われる場合、市町村は、被相続人の生前に心身の状況等の調査を行っていることから、被相続人が、相続の開始の直前において介護または支援を必要とする状態にあったことは明らかであると認められます。
居住用宅地等の課税価格の減額割合と適用限度面積
減額割合
居住用宅地等の相続税評価額の100分の80(80%)を減額することができます。
(=相続税評価額の20%のみが、相続税の課税対象となる財産に加算されます。)
≪計算例1≫
居住用宅地の相続税評価額が8,000万円の場合、小規模宅地等の特例を適用しますと、相続税の課税対象となる相続税評価額は、1,600万円になります。
減額・・・8,000万円×100分の80=6,400万円
特例適用後の相続税評価額・・・8,000万円-6,400万円=1,600万円
(=8,000万円×100分の20=1,600万円が相続税の課税価格に加算されます。)
≪計算例2≫
相続人が配偶者と子2人で、相続財産が居住用宅地8,000万円と家屋1,000万円、預貯金2,000万円の相続のケースで計算してみます。
①遺産に係る基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
②小規模宅地等の特例を適用できない場合
相続財産総額 8,000万円+1,000万円+2,000万円=1億1,000万円
1億1,000万円-4,800万円=6,200万円➡この6,200万円に相続税が課税されます。
③小規模宅地等の特例を適用できる場合
相続財産総額 8,000万円+1,000万円+2,000万円=1億1,000万円
小規模宅地等の特例適用 8,000万円-(8,000万円×100分の80)=1,600万円
課税対象となる相続財産総額 1,600万円+1,000万円+2,000万円=4,600万円
課税対象となる相続財産総額4,600万円は、遺産に係る基礎控除額4,800万円を下回りますので、相続税は課税されないこととなります。
②と③を比較しますと一目瞭然です。『小規模宅地等の特例』を適用できる場合には、相続税の節税にとどまらず、相続税が課税されないこともあります。
(注)『小規模宅地等の特例』の適用により、相続税が課税されないこととなった場合でも、相続税申告書を作成し提出しなければなりません。
適用限度面積
居住用の宅地等に小規模宅地等の特例を適用できるのは、宅地面積330㎡までです。
≪事例≫
被相続人が亡くなるまで居住していた宅地600㎡を、同居している配偶者が相続した場合、小規模宅地等の特例を適用することができます。
但し、特例を適用することができる居住用宅地の面積は330㎡までとなります。
≪計算例≫
宅地600㎡の相続税評価額が1億8,000万円とします。
①特例を適用できるのは330㎡までですので、下記の計算式で特例を適用できる相続税評価額を計算します。
1億8,000万円÷600㎡×330㎡=9,900万円
②小規模宅地等の特例適用により減額できる相続税評価額を計算します。
9,900万円×100分の80(80%)=7,920万円
③特例適用後の宅地の相続税評価額
居住用宅地等の特例を適用できる人とそれぞれの適用要件
特例を適用することができる人は、相続または遺贈により被相続人等の居住用宅地等を取得した次の人たちです。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人と同居していた親族
- 持ち家のない、被相続人と別居の親族
- 被相続人と生計を一にしていた親族
特例適用のためには、上記の『特例を適用することができる人』が、さらに満たさなければならない要件があります。続いて、それぞれの要件を見ていきましょう。
『被相続人の配偶者』についての要件
被相続人の配偶者については、被相続人等の居住用宅地等を取得するのみで、特例を適用することができます。
『被相続人と同居していた親族』についての要件
被相続人と同居していた親族については、次の要件をすべて満たしていれば特例を適用することができます。
- 被相続人の居住用宅地等を取得すること。
- 相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き、その居住用宅地等を所有していること。
- 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続き、その居住用宅地等に居住していること。
【同居について】
『同居』とは、『一つの家に二人以上の人が一緒に住むこと』、または、『ある家族の家にその家族以外の人が住むこと』を意味します。
小規模宅地等の特例の規定においても、『同居』は被相続人と『一棟の建物』に一緒に住んでいることを意味しています。
この『一棟の建物』が『建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物』である場合には、被相続人が居住していた部分のみが特例の対象となります。
【二世帯住宅の取扱い】
平成25年の税制改正により、平成26年1月1日以後の相続開始から二世帯住宅における『同居』の要件が緩和されています。
二世帯住宅については『同居』の要件を、『住宅内部で行き来ができる構造であるか否か』という点で判定していました。つまり、住宅内部で行き来ができる構造の二世帯住宅は、被相続人と親族が同居していたものと解し、全体を一つの住居と捉え、二世帯住宅の敷地である宅地全体を小規模宅地等の特例の適用対象であると認めていました。
他方、住宅内部で行き来ができない構造の二世帯住宅は、区分ごとに独立した住居であると捉え、被相続人が居住していた部分は、他の要件を満たせば小規模宅地等の特例の適用対象と認められるものの、それ以外の部分は、特例の適用対象には該当しないものとされていました。
外見上は同じ二世帯住宅であるのに、内部の構造の違いにより課税関係が異なるのは不合理であるとの指摘を踏まえ、二世帯住宅の取扱いが見直されました。
二世帯住宅であれば、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、住宅全体に二世帯が同居しているものとして、二世帯住宅の敷地等の全体に特例を適用することが可能となりました。但し、二世帯住宅に区分所有建物の登記がなされていないことが要件となります。
『持ち家のない、被相続人と別居の親族』についての要件
『持ち家のない、被相続人と別居の親族』は、俗に『家なき子』と言われています。『家なき子』が小規模宅地等の特例を適用するための要件は、細かく規定されていますので、注意深くチェックしましょう。
以下では、『持ち家のない、被相続人と別居の親族』を『別居の親族』と書きます。
- 被相続人に配偶者がいないこと。
- 相続開始の直前において、被相続人と同居していた相続人がいないこと。
- 相続開始前の3年以内に、別居の親族等が所有していた日本国内にある家屋(★1)に居住したことがないこと。
- 相続開始のときに、別居の親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時にも所有していたことがないこと。
- 取得した居住用宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで所有していること。
- 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有している者であること。
(★1)『別居の親族等が所有していた日本国内にある家屋』とは、下記に該当する家屋です。
- 別居の親族自身が所有する日本国内にある家屋
- 別居の親族の配偶者が所有する日本国内にある家屋
- 別居の親族の三親等内の親族が所有する日本国内にある家屋
- 別居の親族と特別の関係がある法人(★2)が所有する家屋
(★2)『特別の関係がある法人』とは、下記に該当する法人です。
1.別居の親族および次に掲げる者が、法人の発行済株式または出資の総数または総額(以下『発行済株式総数等』と書きます。)の10分の5(50%)を超える数または金額の株式または出資を有する場合における当該法人
イ.別居の親族の配偶者
ロ.別居の親族の三親等内の親族
ハ.別居の親族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ニ.別居の親族の使用人
ホ.イから二までに掲げる者以外の者で、別居の親族から受けた金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ヘ.ハからホまでに掲げる者と生計を一にする、これらの者の配偶者または三親等内の親族
※以下では『別居の親族』と『上記イからヘの者」とを『別居の親族等』と書きます。
2.別居の親族等および上記『1』に該当する法人とが、他の法人の発行済株式総数等の10分の5(50%)を超える数または金額の株式または出資を有する場合における当該他の法人
3.別居の親族等および上記『1』『2』に該当する法人とが、他の法人の発行済株式総数等の10分の5(50%)を超える数または金額の株式または出資を有する場合における当該他の法人
4.別居の親族等が理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものとなっている持ち分の定めのない法人
『被相続人と生計を一にしていた親族』についての要件
遺産分割が完了していることが大前提
前項目の『居住用宅地等の特例を適用できる人』に記載しているように、この特例を適用できるのは、特例を適用したい土地等を取得した人です。『取得した』ということは、相続人間の遺産分割協議を終えて、その人が土地等を相続し取得することが確定しているということを意味します。
従いまして、小規模宅地等の特例を適用するための大前提として遺産分割協議が整い、相続人の誰がどの財産を承継取得するのかが決まっていることが必要です。少なくとも、小規模宅地等の特例を適用したい土地等を相続し取得する人が決まっていることが必要です。
相続税の申告期限までに遺産分割が完了していることが特例適用の大前提となります。
但し、どうしても相続税の申告期限内に遺産分割協議が完了しなかった場合には、救済措置が設けられています。『遺産が未分割の場合の相続税申告』をご覧ください。
- 相続不動産の税金
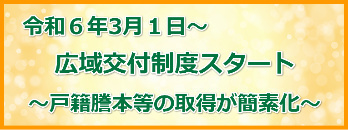
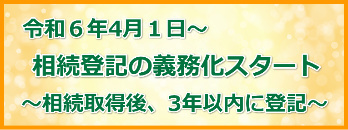
ご連絡先&アクセス
地図
小林佳与公認会計士・税理士事務所
住所
〒143-0023
東京都大田区山王2-1-8
山王アーバンライフ310
JR京浜東北線根岸線・大森駅
北口より徒歩1分
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。

