相続のことなら『東京相続なんでも相談ルーム』へご相談下さい。
休日:土曜・日曜・祭日
居住用財産を譲渡したときの3,000万円特別控除
『居住用財産を譲渡したときの3,000万円特別控除』とは、個人が居住している(居住していた)家屋または居住している(居住していた)家屋とその敷地等(※)を売却した場合には、譲渡所得額から最高3,000万円を控除することができる特例です。
譲渡所得額から3,000万円を控除することで、譲渡所得税が軽減されたり、または、譲渡所得税が課税されないこととなります。
居住用の家屋とその敷地等(※)を売却する際に活用できる特例です。利用するときには、適用要件を十分に御検討ください。専門家に確認してもらうと安心です。
(※)その敷地等・・・その家屋の敷地または借地権のこと。
生前に居住している家屋とその敷地等を売却・換金する場合や、相続し居住している家屋とその敷地等を売却する場合には、3,000万円特別控除の特例の活用を検討しましょう。
計算事例
譲渡所得の金額は、次の算式で計算されます。
収入金額-(取得費+譲渡費用)=長期(短期)譲渡所得金額
特例の適用により、上記の算式で計算された、長期(短期)譲渡所得金額から最高3,000万円を控除することができます。
【設例】
10年間、自己の居住に使用していた土地家屋を、他人に6,000万円で譲渡しました。取得費は2,500万円、譲渡費用は300万円です。譲渡所得金額および譲渡所得税額はいくらでしょうか。3,000万円特別控除の特例の要件を満たしています。
<長期譲渡所得金額>
6,000万円-(2,500万円+300万円)=3,200万円
<譲渡所得税額>
3,200万円-3,000万円(特別控除)=200万円
200万円×15%=30万円
※設例では復興特別所得税を省略し、長期譲渡所得税率15%を使って計算しています。
適用要件
この特例の適用要件は、次のとおりです。
1 | 自己が居住している家屋または自己が居住している家屋とその敷地等の売却であること。 |
| 2 | 居住用家屋等を売却した年の前年または前々年にこの特例を利用していないこと。 |
| 3 | 『特別の関係にある者』に対する譲渡ではないこと。(下記『特例を適用できない場合(1)』をご参照ください。) |
| 4 | 『他の特例』を適用していないこと。(下記『特例を適用できない場合(2)』をご参照ください。) |
| 5 | 【過去に居住していた家屋等を譲渡する場合】 居住しなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。 |
| 6 | 【居住していた家屋を取壊して敷地等のみを譲渡する場合】 居住していた家屋を取壊した日から1年以内に譲渡契約が締結され、かつ、その家屋に居住しなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。 |
| 7 | 【居住していた家屋を取壊して敷地等のみを譲渡する場合】 居住していた家屋を取壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地等を貸付けその他の用途に利用していないこと。 |
| 8 | 【災害により居住していた家屋が滅失した場合】 災害により滅失した家屋に居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。 |
適用要件についての留意事項
『居住用財産を譲渡したときの3,000万円特別控除』の特例は、長期所有の居住用家屋等でも短期所有の居住用家屋等でも適用できます。
原則として、居住用家屋の譲渡に認められる特例ですので、その敷地等は、家屋とともに譲渡する場合のみ適用対象となります。これは、家屋とその敷地等の所有者は同一であることを前提としているからです。(但し、一定の要件を満たせば、敷地等のみの譲渡にも適用できます。上表『適用要件6、7』参照)
例えば、敷地の所有者が夫であり、家屋の所有者が妻であるケースでは、原則として、家屋所有者の妻にのみ3,000万円特別控除が適用され、土地所有者の夫には、特別控除は適用されません。但し、一定の要件を満たせば、このようなケースでも夫婦ともに特別控除が適用されます。
上記のように、居住用の家屋と敷地等の権利関係などにより、特例の適用要件を満たしているかどうか迷うケースも多々あります。そのような場合には、専門家にご相談することをお薦め致します。
特例が適用できない場合
居住している(居住していた)家屋等を『特別の関係にある者』に譲渡した場合や、『他の特例』を選択適用している場合には、『居住用不動産を譲渡したときの3,000万円特別控除』の特例を適用することはできません。ここでは『特別の関係のある者』『他の特例』について解説します。
『特別の関係がある者』について
『特別の関係がある者』とは、居住用財産を譲渡した個人と下表のような特別の関係がある人のことです。『特別の関係がある者』について、租税特別措置法施行令第20条の3に規定がありますので、下表に簡潔にまとめました。
| 1 | その個人の配偶者および直系血族。 |
| 2 | その個人と生計を一にしている親族。居住用不動産の売却後、その個人とその居住用不動産に共に居住する親族。 |
| 3 | その個人と婚姻の届出をしていない事実婚の関係にある者、および、その事実婚の関係にある者と生計を一にしている親族。 |
| 4 | 上記1から3の者およびその個人の使用人以外の者で、その個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者、および、その者と生計を一にしているその者の親族。 |
| 5 | その個人等と特殊の関係にある法人。 |
※表中の『その個人』は『居住用財産を譲渡した個人』のことです。
譲渡する相手が『特別の関係にある者』であるかどうかの判定は、譲渡したときの状況により判定します。(2の『共に居住する親族』であるかどうかは、譲渡後の状況により判定します。)
『他の特例』について
『居住用財産を譲渡したときの3,000万円特別控除(措置法第35条第2項)』の特例は、『他の特例』の適用を受けている場合には適用できません。
それでは『他の特例』とは何なのか。次の2つ(①と②)に分けて、それぞれについて表にまとめます。
- ①…居住用財産を譲渡した前年、前々年にすでに適用を受けている特例
- ②…居住用財産の譲渡について、選択適用した他の特例
①前年、前々年に適用を受けている特例
| 1 | 措置法第35条第2項 | 居住用財産の3,000万円特別控除 |
| 2 | 措置法第36条の2 | 特定の居住用財産の買換えの特例 |
| 3 | 措置法第36条の5 | 特定の居住用財産の交換の特例 |
| 4 | 措置法第41条の5 | 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除 |
| 5 | 措置法第41条の5の2 | 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除 |
上表の1から5までの特例を、前年または前々年に適用している場合には、本年度の居住用財産の譲渡について『3,000万円特別控除』特例の適用はできません。
①の規定により、自己の居住用財産を譲渡したときの『3,000万円特別控除』特例は、3年に一度の適用に限定されていることが分かります。
②適用を選択した特例
| 1 | 所得税法第58条 | 固定資産の交換の特例 |
| 2 | 措置法第33条 | 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 |
| 3 | 措置法第33条の2 | 交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例 |
| 4 | 措置法第33条の3 | 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例 |
| 5 | 措置法第33条の4 | 収用交換等の場合の特別控除の特例 |
| 6 | 措置法第35条の2 | 特定の土地等の長期譲渡所得の特例 |
| 7 | 措置法第37条 | 特定の事業用資産の買換えの特例 |
| 8 | 措置法第37条の4 | 特定の事業用資産の交換の特例 |
| 9 | 措置法第37条の7 | 大規模な住宅地の造成のための交換等の特例 |
| 10 | 措置法第37条の9の4 | 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例 |
| 11 | 措置法第37条の9の5 | 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例 |
居住用財産の譲渡について、上表1から11までの特例を選択適用した場合には、『3,000万円特別控除』特例を適用することはできません。
ただし、譲渡財産が居住用財産と非居住用財産に分けることができる場合などには、『他の特例』とともに『3,000万円特別控除』特例を適用できることがあります。
適用のための手続き
この特例の適用を受ける場合には、居住用家屋等を譲渡した年分の確定申告書等を提出しなければなりません。
居住用家屋等の譲渡所得から3,000万円を控除した結果、課税所得がゼロとなり所得税が課税されないこととなった場合にも、確定申告書等を提出しなければなりません。
提出する書類は次のとおりです。
- 該当年分の確定申告書(『所得税及び復興特別所得税の確定申告書(分離課税用)第三表を使用します。)
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算書)
- 戸籍の附票の写しまたは消除された戸籍の附票の写し(居住用家屋等の譲渡契約日の前日の譲渡者の住民票に記載されている住所と譲渡をした居住用家屋等の所在地が異なる場合に確定申告書に添付しなければなりません。)
- その他添付資料として必要と考えられる書面

不動産譲渡所得税申告サポートサービス
土地・家屋の譲渡所得税の申告は、取得費や譲渡費用の範囲の判定とその計算方法など、税法ならではの独特な考え方に基づいた検討が必要です。
『居住用財産を譲渡したときの3,000万円控除』や『相続した空き家を譲渡したときの3,000万円控除』などの特例を利用する際には、厳格な適用要件を満たしているか否かの検討が必要です。
不動産の譲渡は、金額が大きな取引ですので納税額も大きくなります。判断を誤り納税額が過大になるということのないように、専門家の活用をご検討下さい。
- 相続不動産の税金
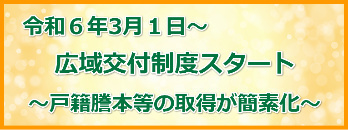
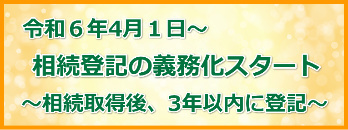
ご連絡先&アクセス
地図
小林佳与公認会計士・税理士事務所
住所
〒143-0023
東京都大田区山王2-1-8
山王アーバンライフ310
JR京浜東北線根岸線・大森駅
北口より徒歩1分
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。

