相続のことなら『東京相続なんでも相談ルーム』へご相談下さい。
休日:土曜・日曜・祭日
相続税の非課税財産
2025.4.10更新
相続税法は、財産の性格上、相続税を課税するのが好ましくないものについては非課税とする規定を設けています。この非課税財産の規定は、国民感情に配慮するとともに、公益性や、社会政策的な見地から必要であるとして定めらたものです。
相続税法に規定されている非課税財産
下記の表は、相続税法等に規定されている非課税財産を、簡潔にまとめたものです。
| 皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が承継するもの | 相続税法第12条①一 |
| 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの | 相続税法第12条①二 |
| 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業の用に供する財産 | 相続税法第12条①三 |
| 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 | 相続税法第12条①四 |
| 相続人が取得した生命保険金等の合計額のうちの一定額 | 相続税法第12条①五 |
| 相続人が取得した退職手当金等の合計額のうちの一定額 | 相続税法第12条①六 |
| 申告書の提出期限までに国等に対して贈与された、相続又は遺贈により取得した財産 | 措置法第70条 |
| 申告書の提出期限までに、災害により被害を受けた相続財産 | 災免法第6条 |
墓所、霊びょう及び祭具等について
墓所、霊びょう及び祭具等は、祖先崇拝の慣習を尊重して非課税とされています。民法第897条にも、祭祀に関する権利の承継についての規定があり、一般の財産とは区分して、特別の配慮が施されています。
相続税法基本通達に示されている具体例は次のとおりです。
| 墓所、霊びょうの具体例 | 墓地、墓石、おたまや | 相基通12‐1 |
| 祭具等の具体例 | 庭内神し、神棚、神体、神具、仏壇、位牌、仏像、仏具、古墳、日常礼拝に供しているもの | 相基通12‐2 |
| 非課税とならないものの具体例 | 商品、骨とう品、投資の対象として所有するもの(金の仏像等) | 相基通12‐2 |
【ご参考】民法第897条第1項
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(相続の一般的効力)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
生命保険金等の非課税限度額について
みなし相続財産である生命保険金等には、非課税限度額が設けられています。「保険金の非課税限度額」は、500万円に法定相続人の数を乗じた金額です。
保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
ここでの法定相続人の数は、相続を放棄した人がいる場合でも、その相続放棄がなかったものとして取扱いますので、民法第5編第2章に規定されている相続人の数となります。
法定相続人の数に含める養子の数の制限規定も適用されますので、ご確認下さい。
注意点は、相続を放棄した人には、生命保険金等の非課税限度額の規定は適用されないという点です。相続を放棄しても、生命保険金等を取得していると、その生命保険金等に相続税が課税されますが、非課税規定は適用されないこととなりますのでご注意下さい。相続を放棄していなければ、生命保険金等の非課税規定が適用されて、相続税が課税されないこととなる場合もあります。相続を放棄するのか否かの判断に際しては、この点も慎重に検討する必要があります。
退職手当金等の非課税限度額について
みなし相続財産である退職手当金等にも、非課税限度額が設けられています。生命保険金等の非課税限度額と同様の規定です。
退職手当金等の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
法定相続人の数は、相続を放棄した人がいる場合でも、その相続放棄がなかったものとして取扱いますので、民法第5編第2章に規定されている相続人の数となります。
法定相続人の数に含める養子の数の制限規定も適用されますので、ご確認下さい。
退職手当金等の非課税限度額の規定も、相続を放棄した人には適用されませんのでご注意下さい。相続を放棄していなければ、非課税規定の適用により、相続税が課税されずに済んだところ、相続を放棄したがために、相続税が課税されるということも想定されます。相続を放棄するのか否かの判断は、慎重になさって下さい。
- 相続不動産の税金
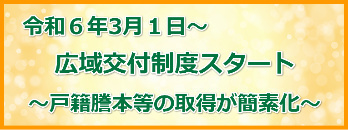
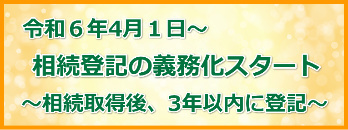
ご連絡先&アクセス
地図
小林佳与公認会計士・税理士事務所
住所
〒143-0023
東京都大田区山王2-1-8
山王アーバンライフ310
JR京浜東北線根岸線・大森駅
北口より徒歩1分
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。

