相続のことなら『東京相続なんでも相談ルーム』へご相談下さい。
休日:土曜・日曜・祭日
遺産に係る基礎控除額について
2025.4.13更新
相続税は、すべての相続財産に対して課税される税金ではありません。
亡くなられた方(被相続人)の遺産総額が一定の金額を超えた場合に、その相続人や受遺者に相続税が課税されることとなります。
この『一定の金額』が『遺産に係る基礎控除額』です。遺産総額が『遺産に係る基礎控除額』を超える場合に、相続税が課税されるのです。
遺産に係る基礎控除額の計算
『遺産に係る基礎控除額』は、一律の金額ではなく計算式を用いて算出します。計算式は次のとおりです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
【計算例1】
法定相続人の数が3人の場合、『遺産に係る基礎控除額』は、次のとおり計算されます。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
この場合、遺産総額が4,800万円を超えていれば、相続税の課税対象となります。
【計算例2】
法定相続人の数が5人の場合、『遺産に係る基礎控除額』は、次のとおり計算されます。
3,000万円+(600万円×5人)=6,000万円
この場合、遺産総額が6,000万円を超えていれば、相続税の課税対象となります。
【計算例1】【計算例2】からお分かりのとおり、『遺産に係る基礎控除額』は、法定相続人の数が増えるほど、大きくなります。そうしますと、相続税の課税対象にならないように、法定相続人の数を意図的に増やして『遺産に係る基礎控除額』を大きくしようとする人が現れることが容易に想定されます。
そこで、『法定相続人の数』については、意図的に調整することができないように規定が設けられています。
相続税が課税されるかどうかを確かめる
相続税は、すべての相続財産に対して課税される税金ではありません。
遺産を相続した方、遺産を相続する予定の方は、先ずは『遺産に係る基礎控除額』を計算して、遺産総額が『遺産に係る基礎控除額』を超えるか否か、言い換えますと、相続税が課税されるか否かを確かめましょう。
【計算例】
夫婦2人と子供2人の家庭で、父親が亡くなり遺産総額8,000万円を遺したとします。
このとき、相続人は配偶者である妻と子2人ですので、法定相続人の数は3人となります。
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
課税の対象となる遺産額は、遺産総額から『遺産に係る基礎控除額』を差引いた価額ですので、次の算式で計算されます。
課税の対象となる遺産の額=8,000万円-4,800万円=3,200万円
『遺産に係る基礎控除額』を超える3,200万円に対して相続税が課税されることとなります。
相続が開始した場合だけではなく、生前対策を検討する場合も、①遺産総額を概算し②法定相続人の数を確定させ、③『遺産に係る基礎控除額』を計算し把握することが、相続税計算の第一歩となります。
ご参考
平成25年度税制改正
現行法のもとでの『遺産に係る基礎控除額』は、次の計算式で算出されます。
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
この計算式は、平成25年度税制改正により改正されたものであり平成27年1月1日から適用されています。
平成27年1月1日より前に開始した相続については、『遺産に係る基礎控除額』は次の計算式で算出されていました。
遺産に係る基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
この計算式を、上記の【計算例】に当てはめてみますと、遺産に係る基礎控除額は8,000万円となります。遺産総額は8,000万円ですので、8,000万円-8,000万円=0となり、相続税は課税されないこととなります。
平成27年1月1日より前の相続では、現在よりも『遺産に係る基礎控除額』が大きく課税の対象となるケースも少なかったので、相続税は一部の富裕層が対象の税制と考えられていました。
平成27年1月1日以降は、課税の対象となる相続件数は増加し、相続税制はもはや一部の富裕層のみを対象とした税制とは言えなくなってきました。
- 相続不動産の税金
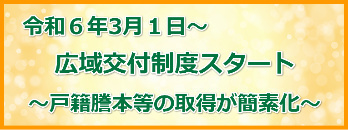
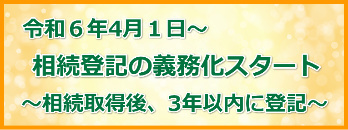
ご連絡先&アクセス
地図
小林佳与公認会計士・税理士事務所
住所
〒143-0023
東京都大田区山王2-1-8
山王アーバンライフ310
JR京浜東北線根岸線・大森駅
北口より徒歩1分
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。

