相続のことなら『東京相続なんでも相談ルーム』へご相談下さい。
休日:土曜・日曜・祭日
債務控除について
2025.4.24更新
相続の開始により、相続人は、被相続人の所有していた資産と負債、言い換えますと、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて承継します。
相続税が課税される財産の価額は、プラスの財産価額からマイナスの財産価額を差し引いて算出します。
このように、マイナスの財産とされる債務と葬式費用をプラスの財産から差し引くことを債務控除と言います。
葬式費用は被相続人のマイナスの財産ではありませんが、相続税法上、プラスの財産から差し引くことが認められています。
債務控除額=被相続人の債務+被相続人に係る葬式費用
債務控除の適用対象者と控除できる債務等の範囲が定められていますので、以下にご説明致します。
債務控除の適用対象者と控除できる債務等の範囲
「債務控除額=被相続人の債務+被相続人に係る葬式費用」であることから、「控除できる債務等の範囲」は、「被相続人の債務」と「被相続人に係る葬式費用」に大きく区分されます。
「控除できる債務等の範囲」の区分ごとに、「被相続人の債務を控除できる者」と「被相続人に係る葬式費用を控除できる者」について細かく規定されています(相続税法第13条)。
①被相続人の債務を控除できる者
被相続人の債務をプラスの相続財産から控除することができるのは、相続人と包括受遺者のみです。相続人と包括受遺者は、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を包括的に承継することから、債務控除の適用対象者であることが理解できます。特定受遺者は、ある特定の財産のみを取得することから、プラスとマイナスの差引は考慮されません。相続人と包括受遺者以外の者は、被相続人の債務を控除することは出来ません。
つぎに、相続人と包括受遺者が「居住無制限納税義務者」「非居住無制限納税義務者」「制限納税義務者」のいずれに該当するのかによって、控除できる債務の範囲がさらに細かく規定されています。
規定の内容を表にまとめました。
| 適用対象者の区分 | 納税義務者の区分 | 控除できる債務の範囲 |
| 相続人・包括受遺者 | 居住無制限納税義務者 | 相続開始の際、現に存在する債務 |
| 非居住無制限納税義務者 | 相続開始の際、現に存在する債務 | |
| 制限納税義務者 | 相続した国内財産に係る債務等 | |
| 被相続人の国内営業所等に係る債務 | ||
| 相続人・包括受遺者以外 | 債務控除の適用なし | |
②被相続人に係る葬式費用を控除できる者
被相続人に係る葬式費用をプラスの相続財産から控除できるのは、相続人・包括受遺者・相続を放棄した者・相続権を失った者です。被相続人の債務を控除できる者と適用対象者が若干異なります。
相続を放棄した者と相続権を失った者は、相続人ではないので、本来は、債務控除の規定は適用されません。しかし、相続を放棄した者や相続権を失った者は、被相続人の親族なので、葬式費用を負担することは現にあり得ます。このような社会的実情に鑑みて、相続を放棄した者や相続権を失った者が、遺贈により財産を取得した場合には、負担した葬式費用の控除を認めているのです(相基通13-1)。
表にまとめますと次のとおりです。
| 適用対象者 | 納税義務者の区分 | 控除の可否 | |
| 相続人 包括受遺者 | 居住無制限納税義務者 | 葬式費用を控除できる。 | |
| 非居住無制限納税義務者 | 葬式費用を控除できる。 | ||
| 制限納税義務者 | 葬式費用を控除できない。 | ||
| 相続人 包括受遺者以外 | 相続放棄者 相続権喪失者 | 居住無制限納税義務者 | 葬式費用を控除できる。 |
| 非居住無制限納税義務者 | 葬式費用を控除できる。 | ||
| 制限納税義務者 | 葬式費用を控除できない。 | ||
| その他 | 債務控除の適用なし。 | ||
債務控除できる債務
債務控除できる債務は、相続開始の際に現に存在するものであり、確実と認められるものに限られます(相続税法第14条)。
債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要としません。また、債務の金額が確定していなくても当該債務の存在が確実と認められるものについては、相続開始当時の現況によって確実と認められる範囲の金額だけを控除します(相基通14-1)。
公租公課について
債務控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡のときに、債務の確定しているものの金額(=納税義務が確定しているものの金額)です。
そして、被相続人の所得税等で、被相続人の死亡後、相続人および包括受遺者が納付し又は徴収されることとなった税額も控除すべき公租公課に含まれます。
ただし、相続人および包括受遺者の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなった延滞税、利子税、各種の加算税に相当する税額や、地方税法の規定による督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額は、控除すべき公租公課に含まれません(相続税法第14条第2項、相続税法施行令第3条)。
国外転出時課税制度における納税猶予税額について
所得税法第137条の2第1項「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予」の適用を受けていた納税猶予分の所得税額、及び、所得税法第137条の3第1項第2項「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予」の適用を受けていた納税猶予分の所得税額は、債務の確定している公租公課の金額には含まれません。
ただし、被相続人の納付の義務を承継した相続人が、納付することとなった納税猶予分の所得税額等は、この限りではありません(相続税法第14条第3項)。
保証債務について
保証債務について、相続税基本通達14-3では次のように取り扱うこととされています。
- 保証債務については、控除しないこと。ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、当該保証債務者の債務として控除すること。
- 連帯債務については、連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合には、当該負担金額を控除し、連帯債務者のうちに弁済不能者があり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがなく、当該弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合には、その負担しなければならないと認められる部分の金額も、当該債務控除を受けようとする者の負担部分として控除すること。
≪ワンポイントアドバイス≫
実務上、被相続人様の相続開始直前に発生した医療費の未払金は、債務控除の対象となります。
この医療費には介護サービス料なども含めることが出来ますので、相続人様が支払った被相続人様の医療費等の領収証は保管しておきましょう。
債務控除できない債務
相続税の非課税財産の取得、維持または管理のために生じた債務の金額は、債務控除できません(相続税法第13条第3項)。具体的には、次のとおりです。
- 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものの取得、維持または管理のために生じた債務。例えば、被相続人の生存中に墓碑を買い入れ、その代金が未払いであるような場合、当該未払代金は債務控除できません(相基通13-6)。
- 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業用財産の取得、維持または管理のために生じた債務。
※上記1、2は、相続税法第12条第1項第二号、第三号に規定されている非課税財産です。
葬式費用として債務控除できるもの
葬式費用として債務控除できる金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとされています。(相基通13-4)
- 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用。(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
- 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用。
- 1又は2に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの。
- 死体の捜索または死体若しくは遺骨の運搬に要した費用。
葬式費用として債務控除できないもの
次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱われませんので、債務控除出来ません。(相基通13-5)
- 香典返戻費用
- 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
- 法会に要する費用
- 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
≪ワンポイントアドバイス≫
位牌代は、墓碑・墓地と同じ取り扱いにより葬式費用に含めることは出来ません。
- 相続不動産の税金
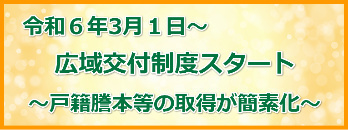
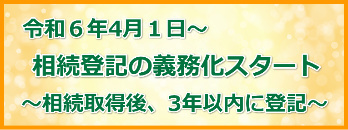
ご連絡先&アクセス
地図
小林佳与公認会計士・税理士事務所
住所
〒143-0023
東京都大田区山王2-1-8
山王アーバンライフ310
JR京浜東北線根岸線・大森駅
北口より徒歩1分
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。

